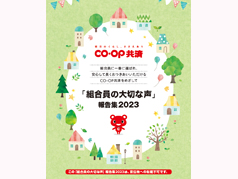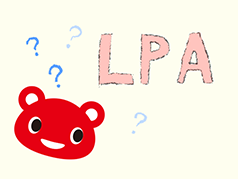福田 真弓氏による
知って得する!くらしとお金の話

いちのせかつみ氏による
知って得する!くらしとお金の話

金田 浩一氏による
知って得する!くらしとお金の話

前野 彩氏による
知って得する!くらしとお金の話

橋本 秋人氏による
知って得する!くらしとお金の話

高山 一恵氏による
知って得する!くらしとお金の話

黒田 尚子氏による
知って得する!くらしとお金の話

望月 厚子氏による
知って得する!くらしとお金の話

青山 雅恵氏による
知って得する!くらしとお金の話

小谷 晴美氏による
知って得する!くらしとお金の話

大江 加代氏による
知って得する!くらしとお金の話