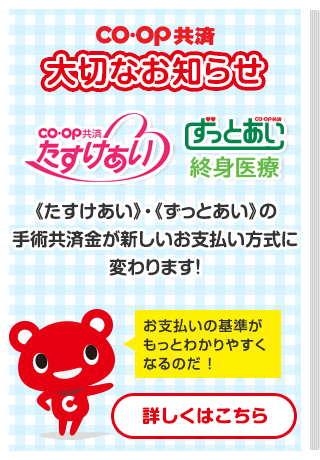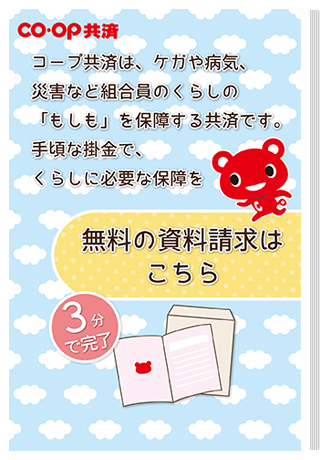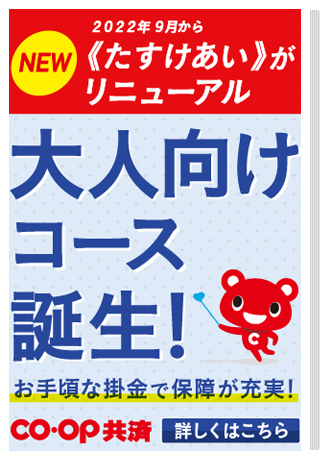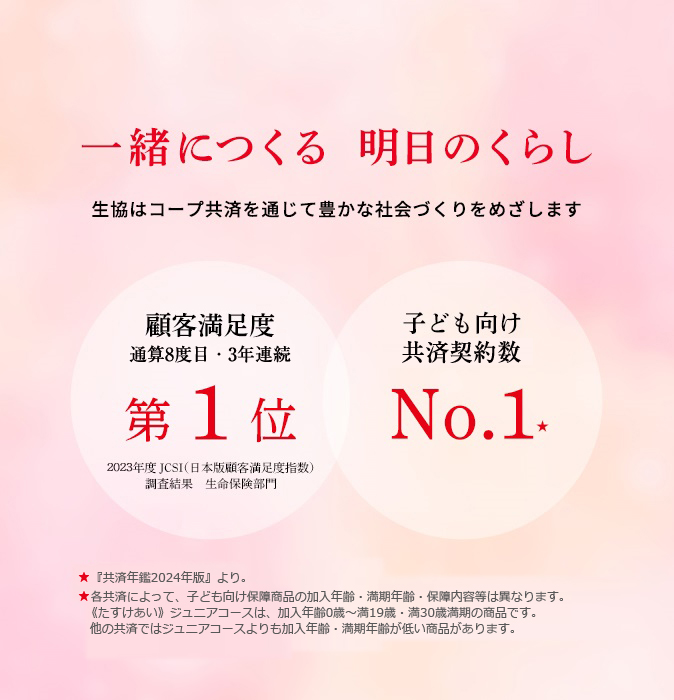
加入をご検討の方
資料請求や新規加入のご相談
(平日)9:00〜17:00 (土曜日)9:00〜16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
ご契約者の方
共済マイページでのお手続きはこちら
24時間いつでも!どこでも!共済のお手続きや保障内容の確認ができます。
\共済マイページでできることの一例/
共済金の請求
契約内容の確認
住所・電話番号の変更
掛金振替口座の変更
共済金のご請求
0120-80-9431
ご加入やご契約
について 0120-50-9431 シニアサポート
ダイアル※1 0120-15-9431
について 0120-50-9431 シニアサポート
ダイアル※1 0120-15-9431
※1:70歳以上の方向けのお問い合わせ窓口になります。
受付時間:9:00〜18:00
(月曜日〜土曜日)※祝日含む
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
コープ共済が
社会のためにできること
共済事業規約・細則
ご契約のしおり

生協組合員だから
団体割引で加入できる
団体割引で加入できる
“コープの団体保険”
はコチラ

採用情報
やるべきことは、
まだまだある。
まだまだある。

保障全般の知識をお知らせする
“生協の保障の考え方
ガイドBOOK”
ガイドBOOK”
はコチラ

コープの組合員が加入できる団体保険
コープ共済ラウンジ
FPによる
知って得する!くらしとお金の話
くらしに役立つ情報を専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)の先生による、生活に関連したお金の話や、くらしに役立つ情報を掲載しています。

FPによる知って得する!くらしとお金の話
mamaomoi
mamaomoi-ママオモイ-は、ママの「知りたい」「学びたい」「作りたい」「遊びたい」「使いたい」という思いをサポートする、ママにやさしい情報サイトです。コープ共済は、大切な家族や子どもの将来について考えるママを応援します。