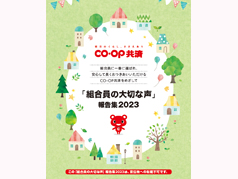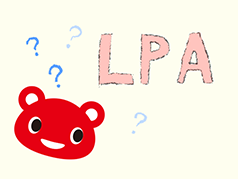2025年7月
みなさんこんにちは。ファイナンシャル・プランナー(CFP®認定者)の金田浩一です。FP専門校のFPK研修センターに勤務しています。FP教育に携わって20年以上の月日が流れました。
前回は、資格を取得した受講生から「得た知識を上手く使えていない」という声に対して、各分野間の知識の連携が上手くいっていないのではと考え、実生活において役立てる例として高額療養費について関連した知識のポイントを整理しました。
今回は別の視点から考えてみたいと思います。実生活で役立てるという点で、知識の整理といいますか押さえておくべきポイントが定まっていないのではと感じることがあります。
FPの知識を習得していくと税制や社会保険制度などについて多くを学びます。いざそれらの制度を実際に利用するにはさまざまな適用要件を満たさなくてはいけません。誰でもみんなそれらの制度を利用できるわけではありません。この点をしっかりと押さえておくべきです。FP知識の整理のポイントとして各種制度の適用要件の理解が重要になってくると思います。
FP知識の整理のポイントの例として、みなさんに身近な住宅ローン控除について考えてみましょう。
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件を満たす住宅の新築や購入、増改築等に際し、返済期間10年以上の住宅ローンを利用した場合に、各年の借入金の年末残高に応じて計算された金額が、所得税から控除できる制度です。所得税で控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除が行われます。
一定の要件を満たすことが必要ですが、住宅ローン控除は減税効果が高い税額控除(所得控除ではない)であるため、とても重要な制度です。一般的な会社員のご家庭では、住宅購入後13年間は所得税がかからないもしくは少額ですむという制度です。
住宅の新築、新築住宅の購入の場合
| 住宅の区分 | 居住開始年と控除対象年末残高 | 控除率 | 最長控除期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
| 認定住宅※1 | 5,000万円 | 4,500万円 | 年末残高×0.7% | 13年 | ||
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | ||||
| 上記以外の一般住宅※2 | 3,000万円 | - | 13年 | |||
| (2,000万円) | 10年 | |||||
- ※1:認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいう。
- ※2:2024年1月以後居住開始の場合は、2023年以前に建築確認を受ける新築住宅に限られ、2024年以後に建築確認を受ける一般住宅は控除対象とならない。
既存住宅の取得、増改築等の場合
| 住宅の区分 | 居住開始年と控除対象年末残高 | 控除率 | 最長控除期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
| 認定、ZEH省エネ、省エネ適合 | 3,000万円 | 年末残高×0.7% | 10年 | |||
| 上記以外 | 2,000万円 | |||||
| 増改築等 | 2,000万円 | |||||
子育て世帯等に対する控除対象年末残高の特例
夫婦のいずれかが40歳未満の人、または19歳未満の扶養親族を有する人(両者を「子育て特例対象個人」といいます)が、認定住宅等の新築等をして2025年1月~12月までに居住を開始した場合、住宅ローンの控除対象年末残高について、2023年居住開始の残高基準が適用される特例があります。
住宅ローン控除の主な適用要件
- 住宅の床面積(登記面積)は50m2以上(一定の場合400m2以上)であり、その2分の1以上が専ら居住用であること。床面積は非居住用部分も含めた面積で判定されます。マンションなどの区分所有建物は専有部分の登記面積となります。
- 2024年以後に居住を開始する新築住宅等の場合は、省エネ基準に適合していること。
- 既存住宅(中古住宅)の場合は、新耐震基準に適合する家屋であること、または登記記録上の建築日付が1982(昭和57)年1月1日以降の家屋であること。
- 住宅取得の日から6ヵ月以内に居住を開始し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること。
- 借入金は、金融機関等からの借入れで返済期間10年以上のものであること。
- 社内融資による借入れ(役員は対象外)については金利が0.2%以上のものであること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 居住を開始した年の前々年から翌年以降3年目にあたる年の年末までに、居住用財産についての3,000万円控除や買換え特例等の適用を受けていないこと。
注意が必要なのは、新築住宅等については省エネ基準に適合していないと住宅ローン控除が受けられないという点です。ただし、2025年4月以降、新築住宅等を建てる場合は、省エネ基準に適合することが義務化されましたので、今後は大きな問題にはならないかもしれません。
上記のように主な適用要件だけでもたくさんあるのですが、住宅ローン控除を受けようとする場合は、手続き的には原則として必要書類を添付して確定申告を行うことが必要です。ただし、一定の給与所得者の場合、2年目以降は年末調整でも控除を受けることができます。
また、住宅ローン控除の適用を受けている間に、転勤などで転居する場合は注意が必要です。単身赴任で自宅に家族が住み続けている場合は、引き続き控除を受けることができますが、家族帯同の転勤の場合、その間は控除を受けることができません。ただし、転勤の際に税務署に一定の手続きをしておくと転勤が終わって自宅に再入居した時に、当初の控除期間の残りがあれば、その間は再び控除を受けることができます。
避けなければならないのは、住宅ローン控除の適用が受けられると思っていたのに、受けられなかったという状況でしょう。適用要件を一つでも満たさなければ適用が受けられないので、しっかり知識を整理しておく必要があります。
さまざまな適用要件を整理していくポイントして、納税者本人が住むための住宅購入のローンに関する特例であるという視点をもって整理しておくのがよいでしょう。
「どういう住宅が対象になるのか」や「いつまでに住み始めなければいけないのか」、「どういうローンであれば対象となるのか」などを押さえておかなければなりません。実際にどういうケースで適用できるかをイメージすることが大切だと思います。
住宅ローン控除の適用期限は今のところ2025年までとなっています。税制改正で延長されると思われますが、適用要件や控除対象年末残高などが見直されて延長されることが通常です。住宅ローン控除の適用要件等は頻繁に変更されますので、改正点に関する知識のブラッシュアップを怠らないようにしておきましょう。

- 金田 浩一(かねだ・こういち)
- ファイナンシャル・プランナー(CFP®認定者、1級FP技能士)。大阪府出身。
大阪教育大学卒業後塾講師を経て、2003年にFP専門校FPK研修センター(株)に入社。大阪事業部にて、主にファイナンシャル・プランナーの養成講座および継続研修等の企画運営・講師やFPテキスト・問題集等のFP教材の編集・執筆など、20年以上FP教育に携わっている。受講生の合格をサポートすべく日々業務にあたっている。