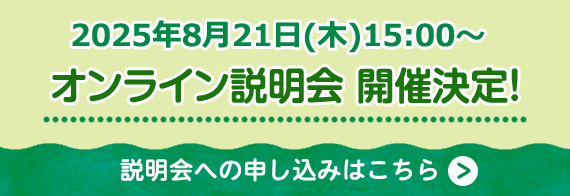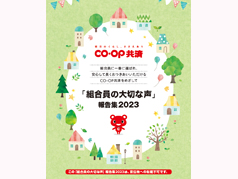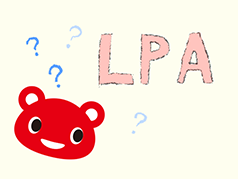ニューストピックス
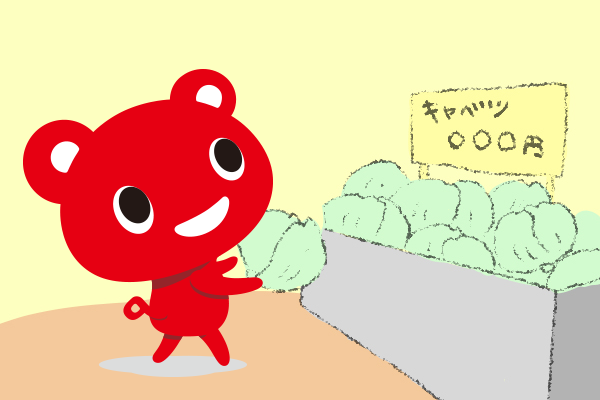
個人情報の取り扱いについて
地域ささえあい助成はコープ共済連がおこなう助成制度ですが、事務局はコープ共済連と日本生協連が協働して運営します。本助成制度を利用するにあたり提供された個人情報は、日本生協連およびコープ共済連双方に提供されたものとして取り扱われます。提供された個人情報につきましては、助成先の審査および本助成制度の運営に必要な範囲で利用し、コープ共済連と日本生協連が責任をもって厳格に管理をおこないます。
お問い合わせ先
本助成制度の事務局は、コープ共済連と日本生協連が協働で担っています。
お問い合わせの内容により、担当が異なりますのでご注意ください。
- 制度全般に関するお問い合わせ先
-
03-6836-1324
(平日10:00~16:00 土日祝日除く)
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)
組合員参加推進部 地域ささえあい助成事務局
- 協働に関する
お問い合わせ・生協紹介のご相談先 -
03-5778-8135
(平日10:00~16:00 土日祝日除く)
日本生活協同組合連合会(日本生協連)
社会・地域活動推進部 地域コミュニティグループ